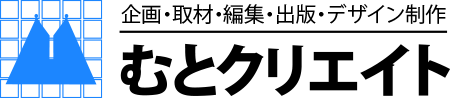2019年9月25日
中村文則著「迷宮」(新潮文庫)
文庫本を買う時は、いつも裏表紙の内容紹介を読みます。この文庫本は、次のように書かれていました。
胎児のように手足を丸め横たわる全裸の女。周囲には赤、白、黄、色鮮やかな無数の折鶴が螺旋を描く――。都内で発生した一家惨殺事件。現場は密室。唯一生き残った少女は、睡眠薬で昏睡状態だった。事件は迷宮入りし「折鶴事件」と呼ばれるようになる。時を経て成長した遺児が深層を口にするとき、深く沈められていたはずの狂気が人を闇に引き摺り込む。善悪が混濁する衝撃の長編。
この作家の場合、本の紹介の一文にたびたび〝衝撃〟が使われていますね。
例えば、こんな感じ。
『遮光』―-黒ビニールに包まれた謎の瓶。私は「恋人」と片時も離れたくはなかった。純愛か、狂気か? 芥川賞・大江賞受賞作家の衝撃の物語。
『悪意の手記』―-いつまでもこの腕に絡みつく人を殺した感触。人はなぜ人を殺してはいけないのか。若き芥川賞・大江賞受賞作家が挑む衝撃の問題作。
本作も、善悪が混濁する衝撃の長編です。
巻末の「文庫解説にかえて」のなかで、「これは僕の十一冊目の本が文庫本になったものになる。僕の小説は大抵暗いのだけど、この小説にはそれだけでなく、どことなく危うさが漂っている」と記しています。
確かに全体のトーンは暗いです。というか、それが中村ワールドの魅力でもあるわけだけど。
物語は、日置事件の遺児である女性と、恋人(僕)との恋愛譚とも言えます。その日置事件とはどんな事件なのか……。
これは迷宮入りの事件で、マスコミでは折鶴事件とも呼ばれています。少々長くなりますが、どんな事件か、本文から抜粋しておきます。
日置事件。
この事件は、再逮捕、再勾留の違法性を問う事例のモデルとして、司法試験の問題集にも記載されていた。一九八八年に起きた、迷宮事件。僕が十二歳の時。マスコミ用の言葉で、折鶴事件とも呼ばれていた。
東京都練馬区の民家で、日置剛史(45)とその妻の由利(39)、そしてその長男(15)が遺体となって発見された事件。長女(12)だけが生き残った。
当時、民家は密室の状態だった。玄関、窓、全てに鍵がかけてあった。ただ一箇所、トイレの窓だけ開いていたが、換気用の小窓で、小さな子供しか入れない。
一家心中の線で捜査が開始される。だが夫、妻、ともに鋭利な刃物での刺殺で、長男は激しく殴打された上に毒を飲まされての致死と判明した。現場に凶器はなかった。夫、妻、ともに自ら刺した跡はなく、いずれも第三者から首を切られた形跡。夫にも、長男と同じく無数に殴打を受けた跡。それは鈍器などによる損傷ではなく、明らかに、人間の拳によるもの。かなり巨体な人間からと思われ、左利き。夫も妻も長男も右利き。長男は痩せた小柄な体型。殴打痕の拳の幅も、家族の誰とも一致せず。
妻の由利は刺殺されていたが、衣服を身につけていない状態。
犯行現場には、遺体を飾るように、無数の折鶴が散乱していた。特に妻の由利の遺体は、その折鶴で埋まっている。その数は全部で三百十二個だったと言われている。指紋の付着がない。
さて、事件から一か月後に、近くに住む無職の男が逮捕されます。しかし、密室の民家にどのように侵入したか不明で、犯行現場で見つかった指紋、毛髪のDNAと一致せず。結局は釈放。事件は迷宮入りするのです。
なんとも複雑な事件です。大人になった遺児と弁護士事務所で働く僕との交際をきっかけに、この事件の真相が次第に明るみになっていきます。最後は遺児である女が、すべてを告白するという構成になっています。
巧みな構成と文章で、一気に読ませます。ほんと、衝撃的な物語です。それにしても、随分と練り込まれた内容で、数々の伏線も見事に回収されていて、すべて納得がいきます。
誰が犯人なのか。密室トリックの謎も、最後にはわかりますが、女の告白が果たしてどこまで真実なのか、それは明かされていません。いくつかの謎が残ったまま。
そうなんです。事件の真相に、僕は疑問を投げかけ、それでも、それらを飲み込み、最終的には女と籍を入れ、共に生きていくのです。女に「……首を絞めて」と言われながら、つまり女は死を望んでいるのですが、殺すこともできずに……。
主人公の僕は、自分のなかにある歪みを Rという別人格に閉じ込めています。小さい頃、愛されなかっただけでこんな大変なことになる僕と女の生き方は、胸を打ちます。
(まあ、こういう世界が嫌いな人もいるでしょうけど、筆者は好きです)
読めば読むほど作者が描く世界から離れられません。この作家が紡ぎ出す物語は、いつも歪んでいますね。でもそこが魅力。ミステリーと純文学の見事な融合と言っていいでしょう。
謎を残しながら、なんとなくハッピーエンドの物語だけど、真相は誰にもわからない。ここに純文学の色合いを感じます。
文庫解説で、作者は、
【人にあまり言えないことの一つや二つ内面に抱えてるのが人間だと思う。無理に明るく生きる必要はないし、明るさの強制は恐ろしい。さらに言えば、「平均」から外れれば外れるほど、批判を受ける確率は高くなっていく。そんな面倒な時代かもしれないけど、小説のページを開く時くらいそこから自由になれるように。共に生きましょう。】と結んでいます。
(北代)