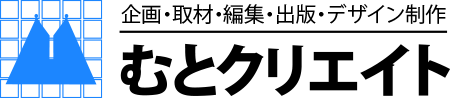2018年1月30日
文豪谷崎の変態性とは?

今回は文豪の作品を取り上げてみたいと思います。つい最近、谷崎潤一郎の「谷崎潤一郎フェティシズム小説集」(集英社文庫)を読んだからです。フェティシズムについて調べていて、どうしても読みたくてアマゾンで購入し、じっくり読んでみました。
短編集なので、「刺青」「悪魔」「富美子の足」「青い花」など、7編が収められています。「刺青」は谷崎のデビュー作ですね。この時代に(明治43年)こんな作品を書いていたなんて、驚きです。まあ、日本では縄文・弥生期に世界でも有数の入れ墨文化を有していたと言われており、特に問題があるわけではないけど。今ならタトウーでしょう。マスコミでも「刺青」はあまり使いませんし……。
【この若い刺青師の心には、人知らぬ快楽と宿願とが潜んでいた。彼が人々の肌を針で突き刺す時、真紅に血を含んで脹(ふく)れ上る肉の疼きに堪えかねて、大抵の男は苦しき呻き声を発したが、その呻き声が激しければ激しい程、彼は不思議にいい難き愉快を感じるのであった。刺青のうちでも殊に痛いといわれる朱刺、ぼかしぼり、――それを用うる事を彼は殊更喜んだ。一日平均五六百本の針に刺されて、色上げを良くするため湯へ浴(つか)って出て来る人は、皆半死半生の体で清吉の足下に打ち倒れたまま、しばらくは身動きさえも出来なかった。その無残な姿をいつも清吉は冷ややかに眺めて、
「さぞお痛みでがしょうなあ」~~】(本文より)
このような痛みの激しい刺青を、主人公の刺青師清吉が16か17の娘に彫り込む。そういう物語です。
【やがて彼は左手の小指と無名指と拇指の間に挿んだ絵筆の穂を、娘の背にねかせ、その上から右手で針を刺して行った。若い刺青師の霊(こころ)は墨汁の中に溶けて、皮膚に滲んだ。焼酎に交ぜて刺し込む琉球朱の一滴一滴は、彼の命のしたたりであった。彼はそこに我が魂の色を見た。】
【二つの人影はそのままややしばらく動かなかった。そうして、低く、かすれた声が部屋の四壁にふるえて聞こえた。
「おれはお前をほんとうの美しい女にするために、刺青の中へおれの魂をうち込んだのだ、もう今からは日本国中に、お前に優る女はいない。お前はもう今までのような臆病な心は持っていないのだ。男という男は、皆なお前の肥料(こやし)になるのだ。……」
その言葉が通じたか、かすかに、糸のような呻き声が女の唇にのぼった。娘は次第次第に知覚を恢復(かいふく)して来た。重く引き入れては、重く引き出す肩息に、蜘蛛の肢は生けるが如く蠕動(ぜんどう)した。
「苦しかろう。体を蜘蛛が抱きしめているのだから」】(本文より)
娘の背中いっぱいに彫られたのは蜘蛛の絵です。描写が秀逸です。娘も、「親方、私はもう今までのような臆病な心を、さらりと捨ててしまいました。――お前さんは真先に私の肥料になったんだねえ」と言うのです。
小説の締めくくりにも、余韻が残ります。
【「帰る前にもう一遍、その刺青を見せてくれ」
清吉はこういった。
女は黙って頷いて肌を脱いだ。折から朝日が刺青の面(おもて)にさして、女の背は燦爛とした。】
また、「富美子の足」は、隠居老人が妾の富美子の足に執着する話。今で言うなら、足(脚)フェチの物語です。足の美しさは言うに及ばず、その足の爪の描写も際立っています。
【普通の獣や人間の爪は「生えている」のですが、お富美さんの足の爪は「生えている」のではなく、「鏤められている」のだといわなければなりません。そうです、お富美さんの足の趾は生れながらにして一つ一つ宝石を持っているのです。もしその趾を足の甲から切り離して数珠に繋いだら、きっと素晴らしい女王の首輪が出来るでしょう。
その二つの足は、ただ無造作に地面を蹈み、あるいはだらしなく畳の上へ投げ出されているだけでも、既に一つの、荘厳な建築物に対するような美観を与えます。】(本文より)
このように細やかな描写が尋常ではなく、さらにその足に踏まれながら息を引き取る老人の姿はフェティシストの極みでしょう。
【~~夕方の五時半に隠居が亡くなるまで、ちょうど二時間半の間、蹈みつづけに蹈んでいたのですから、立っていては足疲(くたび)れてしまうので、枕元へ縁台を据えて腰をかけたまま、右の足と左の足とを代る代る載せていたのでした。隠居はその間にたった一遍、
「有り難う……」
と、微かにいって頷きました。お富美さんはしかし矢っ張り黙っていました。
「まあ仕方がない。もうこれでおしまいなんだから辛抱していてやれ。」というような薄笑いが、~~~」】
隠居とお富美さんの関係性も見事に描かれています。足に拘泥する描写など変態性欲を浮き彫りにさせているのですが、そこに暗さはなく、読後感は爽やかなのです。病的とも思えるほどの描写が、著者も変態ではないかと言われる由縁でしょう。そういう意味では、川端康成とよく比較されますね。
川端の変態性とは?
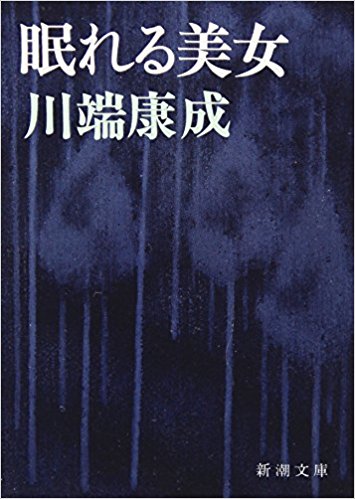
川端の傑作「眠れる美女」は、眠っている美女に添い寝する老人の話です。三島由紀夫は「『眠れる美女』は、形式的完成美を保ちつつ、熟れすぎた果実の腐敗に似た方向を放つデカダンス文学の逸品である。~~その執拗なネクロフィリー(注:死体愛好症)的肉体描写は、およそ言語による観念的淫蕩の極致と云ってよい。」と言っています。
さらに、短編「片腕」は、娘の片腕を借りて老人が一緒に寝る話です。
小説の書き出しは、こんな感じです。
【「片腕を一晩お貸ししてもいいわ。」と娘は言った。そして右腕を肩からはずすと、それを左手に持って私の膝においた。
「ありがとう。」と私は膝を見た。娘の右腕のあたたかさが膝に伝わった。~~】
そして私は娘の片腕と寝るのですが、
【~~そのひとのそばで安心して眠れるのが女はしあわせだと、女が言うのを私は聞いたことがあるけれども、この娘の片腕のように安らかに私に添い寝した女はなかった。】
この片腕は女の言葉でしゃべるし、また物語の後半では、自分の腕と娘の腕を取り換え、肩につけるのです。
【~~自分の右腕を肩からはずして娘の右腕を肩につけかえたのも、私はわからなかった。
「ああっ。」という小さい叫びは、娘の腕の声だったか私の声だったか、とつぜん私の肩に痙攣が伝わって、私は右腕のつけかわっているのを知った。
娘の片腕は――今は私の腕なのだが、ふるえて空をつかんだ。私はその腕を曲げて口に近づけながら、
「痛いの? 苦しいの?」
「いいえ。そうじゃない。そうじゃないの。」とその腕が切れ切れに早く言ったとたんに、戦慄の稲妻が私を貫いた。私はその腕の指をくわえていた。
「……。」よろこびを私はなんと言ったか、娘の指が舌にさわるだけで、言葉にはならなかった。~~~】
取り替えた娘の右腕の指を、私がくわえる。瞬間、戦慄の稲妻が走る。いや~、その発想が川端自身も変態ではないかと言われる由縁だろうか。
Yahoo!の知恵袋に、「川端康成と谷崎潤一郎とではどっちが変態でしょうか?」などという質問があり、その回答に「私は川端康成に一票です。」とあった。筆者も同感です。
作品世界と作者は必ずしも結びつかないだろうが、自らの経験や思想を作品に反映させるのが優れた小説家だと思う。谷崎の足フェチのような特定部位への趣味的嗜好と川端のフェティシズムは性質を異にしますが、「眠れる美女」と「片腕」は「血縁的関係にある作品だ」と評論家も言っています。
文豪川端の考察力には脱帽するしかないけれども、極めて難しい表現方法をとっていて、読み応えがあります。非現実的な世界を描きながら、そこには主人公の孤独が深く漂っているのです。
だから文学になるのだな、と深く感じ入った次第です。
(北代靖典)
[amazonjs asin=”4087466167″ locale=”JP” title=”谷崎潤一郎フェティシズム小説集 (集英社文庫)”]
[amazonjs asin=”4101001200″ locale=”JP” title=”眠れる美女 (新潮文庫)”]