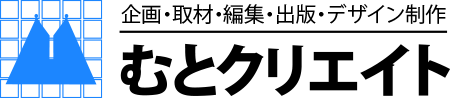2016年7月5日

パニック小説の第一人者として名高い高嶋哲夫さんの新刊の1つです。知り合いでもありますけど、凄いパニック小説を書かれる方です。首都移転の重要性を問う『首都崩壊』、大地震と津波を予見した『M8』『TSUNAMI』、さらにパンデミックによる首都封鎖を描いた『首都感染』、原発の問題に鋭く切り込んだ『メルトダウン』など、数々の話題作を発表し続けています。そんな売れっ子の高嶋さんの、初の純文学です。
書店で購入して、読んでみました。
「今日、僕は、脳だけになった」
衝撃的な帯のキャッチコピーです。
なんだ?
「僕」は、脳だけになったのか?
プロローグの書き出しはこんな感じです。
【「十四の時から四度中絶してるの」
秋子は暗い海を見つめたまま言った。まるで深い海の底に沈んでいくような響きを持つ、静かな声だった。
「子宮がボロボロだからよ。泣きわめいて、子どもなんていらないから早くしまつして、なんて言いだすの」
闇の向こうから波の音が聞こえたような気がする。耳の奥を鋭い刃物でひっかくような耳障りな音だ。胎児の悲鳴。耳をすませたが、今度は聞こえなかった。聞こえるのは車のエンジンの低い唸りだけだ。
「赤ちゃんは頭も出して、必死で生きようとしているのに……」
声には疲れが滲んでいる。昼から夜の九時すぎまで、十時間近く分娩室ですごしたという。医師として体力を使い果たしたのだろう。秋子はK大学医学部付属病院に勤務する産婦人科医だ。
(中略)
対向車線を長距離トラックの巨大な影がかすめる。
僕は先行車のテールランプから目をそらせ、そっと秋子を見た。】主人公は「僕」です。日本の脳研究の最前線を走る医師で本郷秀雄と言いますが、このあと、突然の自動車事故に遭うのです。そして気付けば僕は、一条の光もない闇の中に横たわっていました。「死」――。
「死んだのだ。僕は死んでいる。(中略)では僕は何だ。何なのだ。魂が病室に留まっているとでもいうのか。」
そうなのです。K大学医学部脳神経外科病棟三〇五号室の水槽の中で、「僕」は「脳」だけとなり<生かされて>いたのです。
でも、声は聞こえるので、かつての同僚たちの会話もすべて聞こえるのです。そして恋人だった秋子が生きていたことも、わかります。
さらに、後半、交通事故が仕組まれたものだったということも、判明してくるのです。
刑事が調べているんですね。
【僕はいつも通り半分眠っていました。
谷崎と高杉の声で眼が覚めました。時間はおそらく深夜でしょう。
「久保山って刑事、覚えているか」
「前に来て、色々聞いてた年食ってた方だな。いつもコールテンのブレザー着てる暑苦しい奴」
「あの刑事の野郎、俺を疑ってるんだ。俺が本郷の車のブレーキ管に傷を付けたんじゃないかって、今ごろになって、何なんだよ」
谷崎の怯えを含んだ声が聞こえます。
「おまえ、本当にやってないのか。俺だって、ブレーキ管が傷つけられたって聞いたとき、もしかしたらって思ったよ」
今度は高杉です。
「やめてくれよ。おまえまで。冗談でもそんなこと言うな。刑事は本郷がいなくなればナンバー2は俺だから、それが十分動機になるって。バカバカしい。今どき教授の座なんかを狙ってヤバいことする奴なんていない。テレビドラマや小説じゃあるまいし」
「そんなこと分からないだろ。権力は誰だって握りたい」】
脳だけの僕は、そんな会話を聞いています。感動的なのは、最後のほうで、秋子が「僕」に語りかけるところです。
僕は脳だけですが、脳波を調べる研究材料にもなっているのですね。α波とβ派。僕のそばに、秋子と長谷川がいて、会話をするシーンです。
【「秀雄さんは今目覚めているの」
「おかしいな」
長谷川は計測器を調べているのでしょう。
「β派だ。彼は起きている。しかも、ひどく動揺している」
確かに僕は動揺していました。秋子が取り乱したこと、そして長谷川の言葉は僕を代弁していたからです。
「分かるのよ。秀雄さんには分かってる。ここに私がいることを」
「まさか。でも――」
「あなたたちには分からない。でも、確かよ。秀雄さんは私がいることを知っている。私の声を聞いている」
「興奮しないで。これくらいの乱れは今までにも何度もあったんだ」
「そうじゃない。私には分かる。秀雄さんは私の声を聞いている」
(中略)
「秀雄さん、あなたは本当に生きることを望んでいるの」
秋子が今までとは打って変わって、穏やかな声で問いかけてきます。
「秀雄さん、答えて。私は今でもあなたを愛している。でも……秀雄さんが……こんな姿で……私は……耐えられない……」
秋子! 僕は必死に叫びました。】
本作では、人間における「死」とは何なのかを問いかけています。そして「人間とは何か?」も。構成としては、「K大学医学部脳神経外科病棟三〇五号室」をほぼ舞台にした、「僕」の一人称です。一視点ですので、極めて難しく、言わば「挑戦作」とも言えるでしょう。
まったく違和感はありませんけどね。脳だけになった僕と秋子との恋愛譚でもあります。
(北代靖典)
[amazonjs asin=”4309024475″ locale=”JP” title=”浮遊”]